お役立ち情報
category: 金融業
「説明が難しい…」を解決!金融商品の案内を動画で統一する方法。
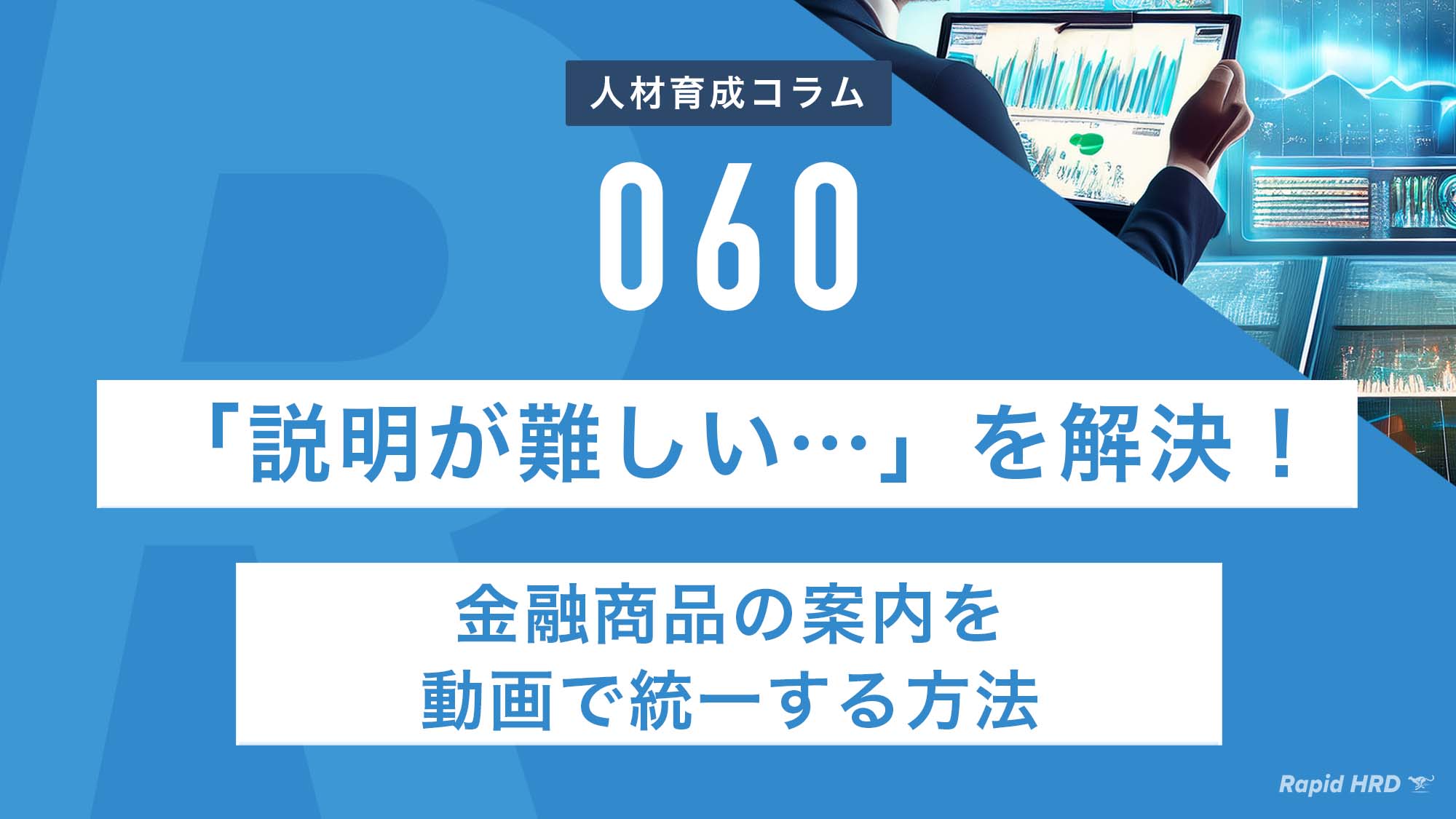
金融商品の説明は、複雑な専門用語や法律が絡み、顧客にとって分かりづらいものになりがちです。担当者ごとに説明の仕方が異なると、顧客満足度にも影響を与えます。
こうした課題を解決する方法として、動画を活用した統一的な説明が注目されています。
本記事では、金融商品の案内を動画で統一するメリットや具体的な活用法について解説します。
▼人材育成を加速する動画マニュアルDXソリューション「RapidHRD」
金融商品の説明が難しい理由とは?
金融商品を顧客に分かりやすく伝えることが難しいのには、いくつかの理由があります。
1. 専門用語が多く、顧客が理解しにくい
投資信託や保険、ローンなどの金融商品は、専門的な用語や概念が多く含まれます。「元本保証」「リスク分散」「流動性」など、金融業界では一般的な言葉でも、顧客にとっては理解しにくいことがあります。
2. 担当者ごとに説明の仕方が異なる
対面での説明では、担当者ごとに話し方や伝え方が異なります。ある担当者はシンプルに説明する一方で、別の担当者は詳細に話しすぎてしまうなど、説明のばらつきが生じやすくなります。その結果、顧客の理解度や満足度に差が出る可能性があります。
3. 法規制に基づいた正確な説明が求められる
金融商品の説明には、法令遵守が求められます。例えば、「誇大広告の禁止」や「リスクの適切な説明」などの規制があり、説明に誤りがあると顧客トラブルや法的リスクにつながる可能性があります。
動画を活用することで得られるメリット
こうした課題を解決するために、動画を活用した統一的な説明方法が有効です。
1. 分かりやすく、顧客の理解を深められる
動画では、アニメーションや図解を用いて、金融商品の仕組みを視覚的に説明できます。例えば、投資信託の仕組みを「水が流れるパイプ」のような図を使って解説することで、顧客が直感的に理解しやすくなります。
2. 説明のばらつきをなくし、一貫した情報提供ができる
動画を活用すれば、全ての顧客に対して同じ品質の説明を提供できます。店舗や担当者ごとの説明の差をなくし、企業全体で一貫性のある案内が可能になります。
3. 法規制に準拠した正確な情報提供ができる
動画は事前に専門家が内容を監修するため、法規制に準拠した正確な説明を提供できます。また、説明内容を変更する際も、動画を更新するだけで済むため、コンプライアンスリスクを抑えながら最新の情報を顧客に伝えられます。
4. 顧客が好きなタイミングで視聴できる
動画は、対面での説明と異なり、顧客が自分のペースで視聴できます。金融商品は一度の説明では理解しきれないことも多いため、後から見返せる動画コンテンツがあると、顧客の満足度が向上します。
金融商品の案内に動画を導入する方法
1. 説明用の動画コンテンツを作成する
まず、主要な金融商品の説明動画を作成します。動画の内容は以下のポイントを意識すると良いでしょう。
- シンプルでわかりやすい表現を使う(専門用語の解説を入れる)
- アニメーションや図解を活用し、視覚的に理解できるようにする
- 顧客の疑問を想定し、FAQ形式の解説を含める
例えば、「住宅ローンの仕組み」を説明する場合、金利の違いや返済プランを図表で見せることで、顧客の理解を促進できます。
2. 店頭やオンラインで動画を活用する
作成した動画は、以下のような場面で活用できます。
- 店頭のタブレットやモニターで流す
- オンライン相談時に共有する
- 自社のホームページや顧客向けポータルサイトで公開する
- パンフレットにQRコードを載せ、スマホで視聴できるようにする
このように、顧客が簡単にアクセスできる仕組みを整えることで、動画の活用効果を最大化できます。
3. 定期的に内容を見直し、最新情報を反映する
金融商品は、法改正や市場環境の変化により、説明内容が変わることがあります。動画コンテンツも定期的に更新し、常に最新の情報を提供できるようにしましょう。
成功事例|動画活用で顧客満足度が向上した金融機関
事例①:大手銀行の住宅ローン説明動画
ある大手銀行では、住宅ローンの説明を動画化し、店頭でタブレットを使って案内するようにしました。その結果、顧客の理解度が向上し、ローン契約率が12%増加しました。担当者の説明時間も短縮され、業務の効率化にもつながっています。
事例②:保険会社の契約内容説明動画
ある保険会社では、生命保険の契約内容を説明する動画を導入し、契約前に必ず視聴してもらう仕組みを作りました。その結果、契約後の問い合わせが30%減少し、顧客満足度が向上しました。
まとめ|動画を活用して金融商品の説明を統一し、顧客満足度を向上させよう
金融商品の説明は、専門用語が多く、担当者ごとにばらつきが出やすいため、顧客が理解しにくいという課題があります。
動画を活用することで、一貫した情報提供が可能になり、顧客が分かりやすく学べる環境を整えることができます。また、法規制に準拠した正確な情報を提供できるため、コンプライアンス対策にも有効です。
店舗やオンライン、パンフレットなど、さまざまな場面で動画を活用し、顧客が納得して金融商品を選べる環境を構築しましょう。
動画マニュアル人材教育の仕組み化なら、「ラピッドHRD」
動画マニュアルDXソリューション「ラピッドHRD」では、動画マニュアルLMSをはじめ、動画マニュアルの制作や活用支援を提供しています。お気軽にお問い合わせください。
▼動画マニュアルDXソリューション「RapidHRD」
コンプライアンス教育に最適!動画で学ぶ金融業界のルールとマナー。

金融業界は、法律や規制に厳格に従うことが求められる業界です。顧客の大切な資産を扱い、社会的責任も大きいため、コンプライアンス違反が企業の信頼を大きく損なう可能性があります。
特に、以下のような分野では厳格なルールが定められています。
- インサイダー取引の防止
- 個人情報の適切な管理
- マネーロンダリング対策
- 顧客への適切な説明義務
- 公正な取引の維持
しかし、コンプライアンス研修は、単なる座学の講義では形骸化しやすく、社員の理解度や定着度にばらつきが出ることが課題となっています。そこで、近年多くの金融機関が導入しているのが、「動画を活用したコンプライアンス教育」です。
本記事では、金融業界における動画研修のメリットと、具体的な活用方法について解説します。
▼人材育成を加速する動画マニュアルDXソリューション「RapidHRD」
動画を活用したコンプライアンス教育のメリット
1. 分かりやすく、直感的に理解できる
コンプライアンス研修では、法律や規則の解説が中心となるため、文字だけの資料では理解しにくいことが少なくありません。動画を活用することで、具体的な事例や映像を交えて説明できるため、従業員はルールを直感的に理解しやすくなります。
例えば、インサイダー取引の禁止についても、単に「内部情報を基に取引をしてはいけない」と説明するのではなく、架空の取引シナリオを動画で再現することで、「どのような行為が違反に当たるのか」「どんな場面で注意すべきか」が明確になります。
2. どこでも学べて、何度でも復習できる
従来の集合研修では、一定の日時に全員が参加する必要がありましたが、動画であれば好きなタイミングで学ぶことができます。
- 新入社員が入社後すぐに受講可能
- 忙しい現場社員も業務の合間に視聴できる
- 法改正があった際に最新情報をすぐに更新・共有できる
また、一度学んだ内容を後から見返すことができるため、「研修を受けたときは理解したつもりでも、しばらく経つと忘れてしまった」という問題も解消できます。
3. 実践的な内容で、現場に即した教育ができる
コンプライアンス違反の多くは、意図的ではなく、「知らなかった」「うっかりやってしまった」というケースが少なくありません。そのため、理論だけでなく、実際の業務で起こりうるケースを学ぶことが重要です。
例えば、
- 「顧客情報をメモした紙をデスクに置き忘れた場合、どう対応すべきか?」
- 「クレーム対応時に、適切な言葉遣いができているか?」
- 「職場内のハラスメントを防ぐために、どんな行動を取るべきか?」
といった 実際の職場で直面するケースを動画で再現 することで、具体的な行動指針を学ぶことができます。
4. 教育の質を統一できる
金融機関では、支店や部署ごとに研修の進め方が異なり、教育の質にばらつきが出ることがあります。動画を活用すれば、全社員に同じ内容の研修を提供できるため、どの支店・部署でも一定のコンプライアンス意識を持つことができます。
また、動画研修の受講履歴をデータとして管理すれば、誰がどの程度学習を進めているかを把握し、未受講者へのフォローも容易になります。
具体的な動画活用法と導入ステップ
1. 研修動画の内容を明確にする
コンプライアンス研修の動画を作成する際は、以下のポイントを意識すると効果的です。
✅ 法令や社内ルールの基礎知識
- 金融商品取引法
- 個人情報保護法
- マネーロンダリング防止策
✅ 実践的なケーススタディ
- 実際に発生したコンプライアンス違反事例の紹介
- 問題発生時の適切な対応例
✅ クイズやチェックテストの導入
- 動画の最後に理解度チェックを実施し、合格者のみ修了とする
2. スマホでも視聴できる環境を整える
研修動画を導入する際は、パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットでも視聴できる環境を用意すると便利です。これにより、移動時間や休憩時間を活用して学習できるようになります。
また、社内のLMS(学習管理システム)と連携させることで、受講状況の管理や進捗の把握が容易になります。
3. 定期的に動画を更新する
金融業界の法規制やルールは、定期的に改訂されるため、一度作成した動画をそのまま使い続けるのではなく、定期的に更新することが重要です。
例えば、「年1回のコンプライアンス研修」を動画形式にするだけでなく、「月1回の短編動画」を配信することで、常に最新情報を学べる環境を整えることができます。
まとめ|動画を活用して金融業界のコンプライアンス意識を高める
コンプライアンス違反は、企業の信用を一瞬で失墜させる重大なリスクです。そのため、全社員が「コンプライアンスを自分ごととして捉え、日々の業務に落とし込むこと」が不可欠です。
動画研修を活用すれば、わかりやすく、実践的に学べるだけでなく、教育の質を統一し、研修の手間を削減 することができます。
金融機関としての信頼を守るために、動画によるコンプライアンス教育を導入し、より強固なガバナンス体制を構築していきましょう。
動画マニュアル人材教育の仕組み化なら、「ラピッドHRD」
動画マニュアルDXソリューション「ラピッドHRD」では、動画マニュアルLMSをはじめ、動画マニュアルの制作や活用支援を提供しています。お気軽にお問い合わせください。
▼動画マニュアルDXソリューション「RapidHRD」
社内研修の手間を削減!金融業の教育に役立つ動画コンテンツ。
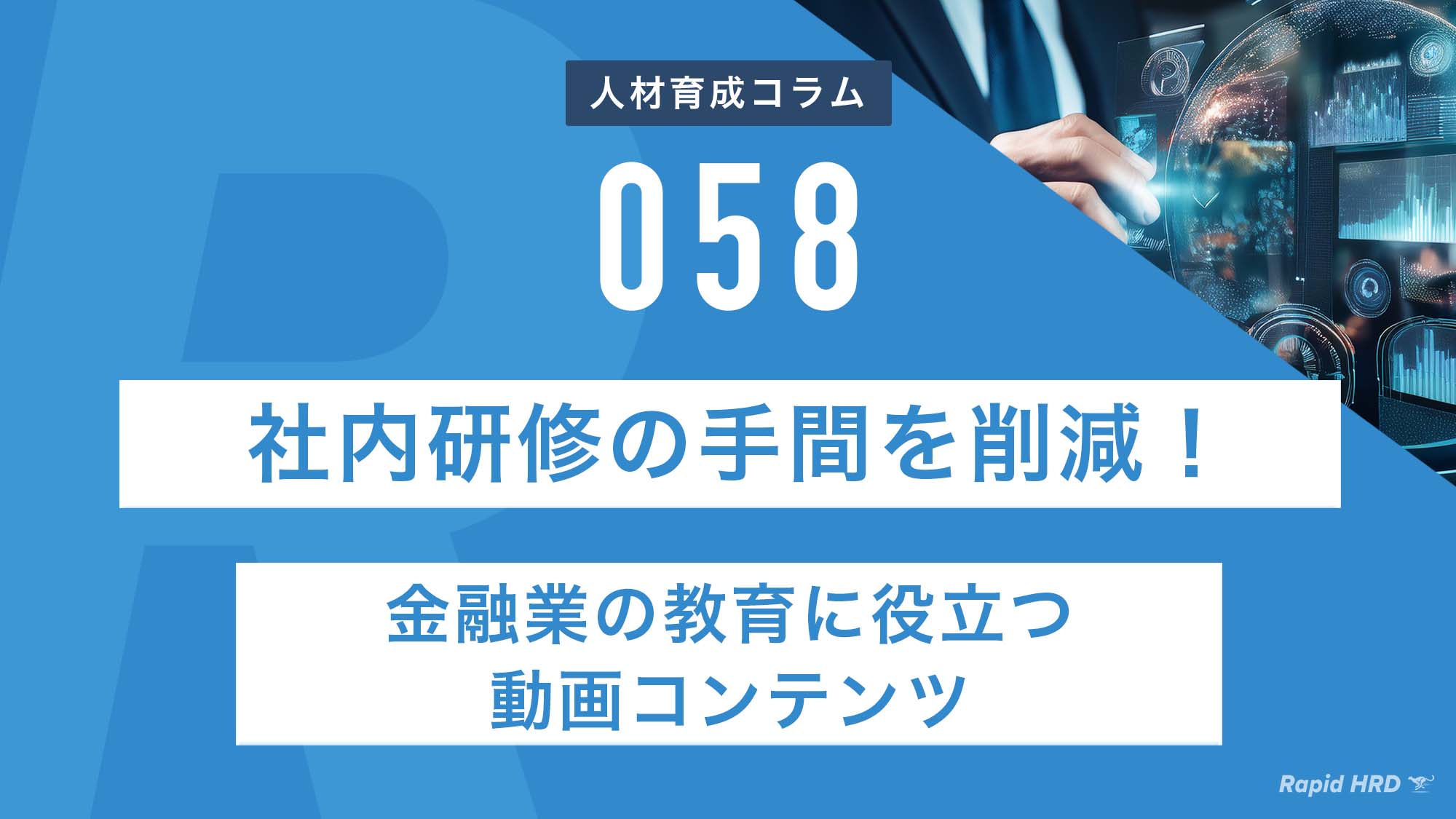
▼人材育成を加速する動画マニュアルDXソリューション「RapidHRD」
はじめに|変革を求められる金融業の人材育成
金融業界は今、かつてない変革の波に直面している。デジタル化の進展、フィンテックの台頭、顧客ニーズの多様化、そして働き方の変化。これらの要因が重なり合う中で、「人材育成」こそが競争力の源泉 となる時代が到来した。
かつて金融機関の研修は、座学中心の集合研修が主流であった。厳格なマニュアルに基づき、上司や教育担当が直接指導する形式が一般的だった。しかし、今日の現場では、以下のような問題が顕在化している。
- 研修にかかる時間とコストが膨大
- 店舗・支店ごとに教育の質がバラつく
- 金融商品・サービスの更新が早く、知識の陳腐化が進む
- OJTに頼るだけでは、経験の浅い社員の成長に限界がある
このような課題を解決する手段として、動画コンテンツを活用した教育体制の構築 が注目されている。本記事では、金融機関における研修の効率化と教育品質の向上を実現するための動画活用の具体的な手法について詳述する。
▼人材育成を加速する動画マニュアルDXソリューション「RapidHRD」
金融業の教育における本質的な課題
1. 教育コストの増大とリソースの逼迫
金融機関の研修は、一般的に階層別・職種別・専門領域別に細分化されている。例えば、新入社員研修、窓口対応研修、融資・投資商品の研修、コンプライアンス研修、営業スキル研修など、網羅すべきテーマは多岐にわたる。
これらの研修を実施するために、企業は多くの時間とコストを投じている。例えば、年間の研修予算が数千万円規模に達するケースも珍しくない。また、教育担当者の負担も重く、「本来の業務と並行しながらの指導は限界がある」 という現場の声も多い。
2. 知識の陳腐化と学習効果の低下
金融業界は、法改正や規制変更、商品・サービスのアップデートが頻繁に発生する。紙のマニュアルや静的な研修資料では、最新情報の反映が追いつかないという問題がある。
また、一度の研修では定着しにくい という点も見逃せない。人間の記憶は、時間とともに自然と薄れていくものであり、継続的な学習機会の提供が不可欠 である。
3. 教育の質のバラつき
各支店や営業所ごとに研修の進め方が異なり、教える人によって内容が変わる ことも大きな課題である。例えば、A支店では「お客様第一」の姿勢を重視する研修を行っている一方で、B支店では「業務効率」を重視した指導がなされているケースがある。
結果として、企業全体としての統一的な接客品質の確立が難しくなる。これが、顧客体験のバラつきやクレーム増加の要因となる。
動画コンテンツによる解決策|金融業の研修を革新する3つの活用法
1. 「オンデマンド研修」で、いつでも学べる環境を構築
動画コンテンツを活用する最大の利点は、「学びたいときに、学べる環境」を提供できること だ。例えば、金融機関向けの動画研修を以下のように設計することで、従業員は自分のペースで必要な知識を習得できる。
📌 基礎編(新入社員向け)
- 銀行・証券・保険業界の基礎知識
- 窓口対応・接客スキル
- 金融商品の基礎知識
📌 実務編(中堅社員向け)
- コンプライアンス・法規制対応
- 投資・融資商品の提案スキル
- ロールプレイ型クレーム対応研修
📌 応用編(管理職向け)
- チームマネジメントとリーダーシップ
- データ分析を活用した営業戦略
- 経営層向けリスクマネジメント研修
動画を活用すれば、従業員は 「必要な時に、必要な内容だけ」 学ぶことができ、集合研修のために時間を割く必要がなくなる。
「インタラクティブ動画」で実践力を鍛える
単なる視聴型の動画ではなく、インタラクティブ要素を取り入れる ことで、学習効果を飛躍的に高めることができる。
例えば、
✅ 「この場面ではどの対応が適切か?」という選択式クイズ
✅ 顧客対応のロールプレイを動画内で疑似体験できるシミュレーション
✅ 視聴完了後に理解度を測るテストを実施し、合格しないと次の動画に進めない仕組み
このような工夫により、受け身の研修ではなく、主体的に学ぶ環境を作る ことが可能になる。
「最新情報の即時共有」で、知識の陳腐化を防ぐ
法改正や金融商品の変更があった場合、動画マニュアルを即座に更新し、全社員にリアルタイムで共有できる仕組みを整える ことが重要だ。
例えば、月に一度の「金融業界ニュース動画」 を配信し、重要な変更点を解説することで、知識のアップデートを効率化できる。
まとめ|金融業の研修を、次のステージへ
動画コンテンツを活用すれば…
✅ 研修時間を短縮し、教育コストを削減
✅ 知識のアップデートを迅速化し、陳腐化を防ぐ
✅ 研修の質を統一し、接客・営業スキルを均一化
変革の時代を迎えた金融業界において、「人材育成の仕組み」そのものを見直すことが、競争力の強化につながる。
動画コンテンツを活用し、未来を見据えた研修体制の構築を、今こそ検討すべきではないだろうか。
動画マニュアル人材教育の仕組み化なら、「ラピッドHRD」
動画マニュアルDXソリューション「ラピッドHRD」では、動画マニュアルLMSをはじめ、動画マニュアルの制作や活用支援を提供しています。お気軽にお問い合わせください。
▼動画マニュアルDXソリューション「RapidHRD」
窓口対応を統一!金融業の接客スキルを動画で学ぶメリット。
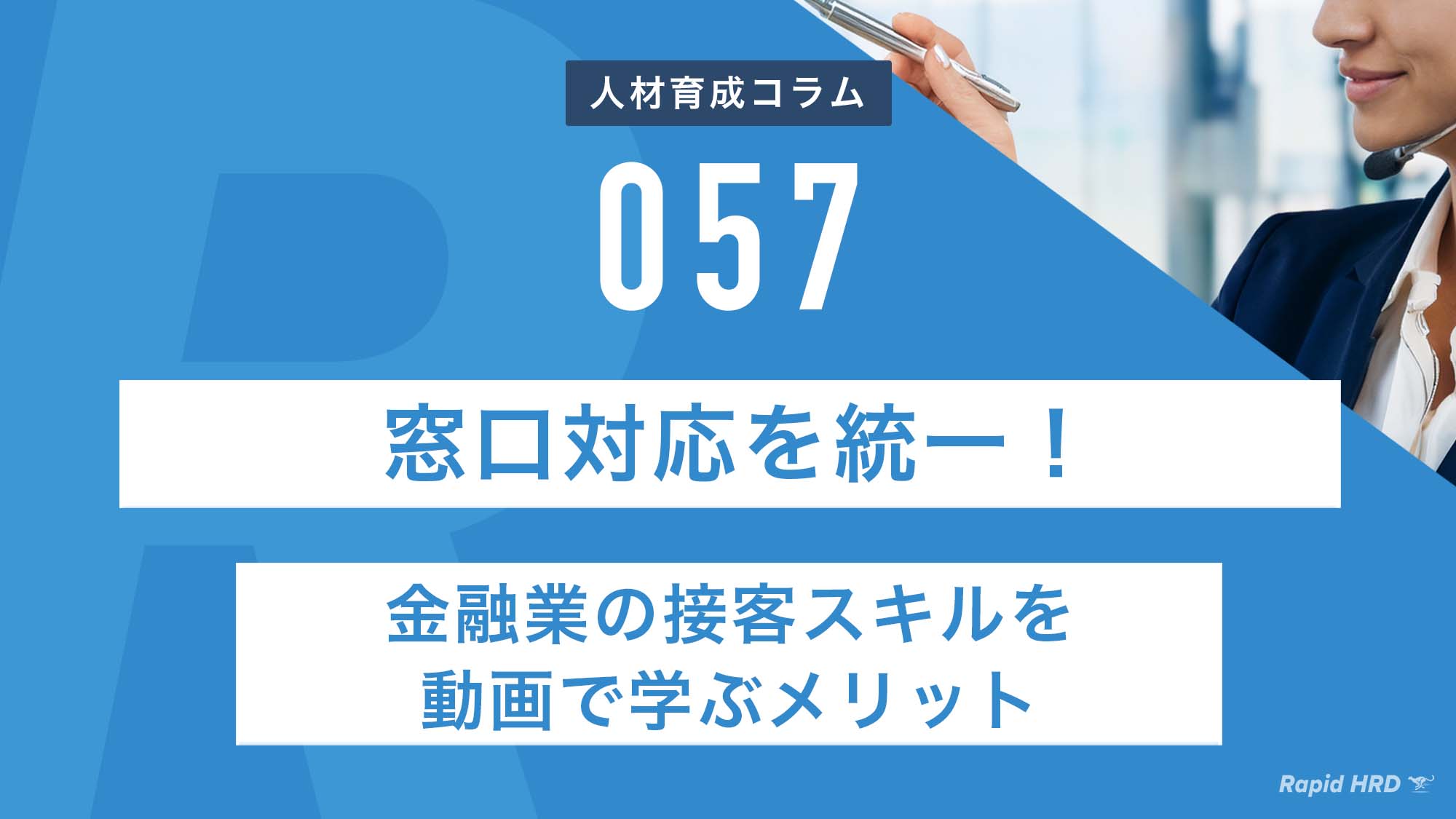
金融機関の窓口対応は、お客様との最前線に立つ重要な業務です。しかし、
- スタッフごとに対応のばらつきがある
- 新人が接客に慣れるまで時間がかかる
- マニュアルを読んでも実践で活かせない
- クレーム対応の基準が統一されていない
- といった課題を抱えている企業は少なくありません。
このような問題を解決する方法として、「動画マニュアル」を活用した統一的な接客トレーニング が注目されています。
本記事では、動画マニュアルを活用して窓口対応を統一し、接客スキルを向上させるメリットと活用方法を詳しく解説します!
▼人材育成を加速する動画マニュアルDXソリューション「RapidHRD」
なぜ金融機関の窓口対応を統一することが重要なのか?
窓口対応の品質が金融機関の信頼を左右する
金融機関の窓口は、お客様が直接サービスを受ける場です。接客の質が
📈 顧客満足度向上 → 信頼の強化
📉 対応のばらつき・ミス → クレーム・信用低下
に直結します。
特に、新人や経験の浅いスタッフが対応する場合、接客レベルの違いが顕著に表れやすく、
❌ 説明不足による誤解
❌ お客様対応の遅延
❌ 不適切な対応によるクレーム発生
といった問題が発生するリスクがあります。
接客のばらつきをなくすには「統一された教育」が必須!
接客品質を一定に保つためには、
- 「誰が対応しても同じレベルの接客ができる」環境づくり
- スタッフが繰り返し学習できる教育システムの整備
が必要です。
そこで、従来の OJT(先輩による直接指導) や 紙のマニュアル に代わり、動画マニュアルを活用する ことで、教育のばらつきを防ぐことが可能になります!
動画マニュアルを活用する3つのメリット
メリット①:視覚的に学べるので、理解しやすい
窓口業務では、
✅ 身だしなみや表情
✅ お客様への言葉遣い・話し方
✅ 書類の受け渡しや端末操作の手順
など、多くの実践的なスキルが求められます。
動画マニュアルなら、実際の業務を「見て学ぶ」ことができるため、紙のマニュアルよりも理解しやすく、即戦力化が早まります!
メリット②:接客品質を統一できる
紙のマニュアルや口頭指導では、教育する人によって教え方が異なるため、
🟢 「Aさんはこのやり方で教わった」
🔴 「Bさんは違う方法を教えられた」
ということが起こりがちです。
しかし、動画マニュアルを導入すれば、
✅ 全スタッフが同じ内容を学習できる
✅ 最新の接客ルールを即座に全員に共有できる
✅ 教育のばらつきを防ぎ、一貫した接客品質を維持できる
というメリットがあります。
メリット③:新人が「繰り返し学習」できるので、教育コスト削減
新人教育の大きな課題の一つが、
📌 何度も同じ説明をする手間がかかる
📌 一度の研修では覚えきれず、再研修が必要になる
という点です。
🎥 動画マニュアルなら…
✅ 必要な時に何度でも見返せる → 定着率アップ
✅ 研修担当者の負担を軽減 → OJTの時間を削減
✅ 「動画を見て学んだうえで現場に入る」仕組みが作れる → 即戦力化が可能
金融機関向け「接客スキル向上のための動画マニュアル」活用例
ケース①:窓口対応の基本を学ぶ動画
例:「初めての窓口業務」マニュアル動画
- お辞儀の仕方・敬語の使い方
- 書類の受け取りや案内の流れ
- ATMや端末の操作方法
ケース②:クレーム対応スキル向上の動画
例:「クレーム対応のNG例とOK例」比較動画
- お客様が怒る理由を分析
- NG対応 → どのように改善すればよいか?
- 実際の現場を再現した対応例
ケース③:金融商品の説明スキルを磨く動画
例:「ローン・投資商品の説明トレーニング動画」
- 難しい金融用語をわかりやすく伝えるコツ
- 提案型営業のスクリプト例
- お客様に安心感を与えるトーク例
効果的な動画マニュアルを作成する3つのポイント
1. シンプルで短く(3〜5分以内)まとめる
ポイントごとに分割し、短時間で学べる構成に!
2. 音声+テキストを組み合わせる
字幕や画面キャプチャを活用し、理解しやすく!
3. 実際の窓口業務を再現する
「実践に役立つ」内容にすることで、現場ですぐ活用できる!
まとめ|動画マニュアルで窓口対応を統一し、接客品質を向上!
動画マニュアルを導入すれば…
- 窓口業務の「ばらつき」をなくし、一貫した接客を実現!
- 新人スタッフの習得スピードを加速し、即戦力化!
- 教育コストを削減し、現場の負担を軽減!
動画マニュアル人材教育の仕組み化なら、「ラピッドHRD」
動画マニュアルDXソリューション「ラピッドHRD」では、動画マニュアルLMSをはじめ、動画マニュアルの制作や活用支援を提供しています。お気軽にお問い合わせください。
▼動画マニュアルDXソリューション「RapidHRD」